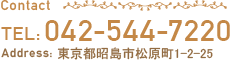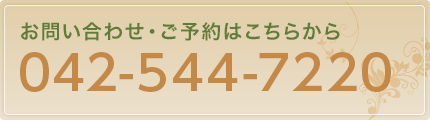顎を動かすと音がするのは顎関節症のせい?原因と顎関節症の対処法
▼目次
1. 口を開けたり顎を動かすと音がなる原因は顎関節症?
2. 顎関節から音はするけど痛みがない場合も顎関節症?
3. 顎関節症で顎を動かすと音がする際の対処法
4. 顎の違和感や口が開かないのも顎関節症のせい?
顎を動かしたときに「カクッ」や「ポキッ」という音が鳴ると、驚くことや不安を感じる方も多いでしょう。これは、顎関節症の症状のひとつです。顎関節症は、顎の関節や周囲の筋肉に音や痛みなど様々な症状が生じます。今回は、顎を動かすと音がする原因や、顎関節症の症状、対処法について解説します。
1. 口を開けたり顎を動かすと音がなる原因は顎関節症?
口を開けたりアゴを動かしたときに音がする原因の一つは、顎関節症による場合があります。顎関節内の関節円板は、顎のスムーズな動きをサポートする役割を持っていますが、顎関節症によってこの円板がずれてしまうことがあります。このずれにより、顎を動かした際に円板が正しい位置に戻ろうとして擦れ合って「カクッ」と音が鳴ります。関節円板のずれは、顎関節症の初期症状として現れることが多いです。ただし、人によっては解剖学的に健全な顎関節でも『コリッ』というような音が鳴ることもあります。これはエミネンスクリックと呼ばれ、病的なものではないので心配しなくても大丈夫ですが、健全な状態か病的な状態かを把握するためには精密な検査が必要となります。音が出るような顎関節症になる主な原因は以下の通りです。
①噛み合わせの不調
噛み合わせが悪いと、両方の顎の関節にアンバランスな力がかかるため、顎の動きがスムーズでなくなり、音が鳴る原因になります。噛み合わせの不良が長期化すると、顎関節症の症状は進行、悪化しやすくなります。
➁頬杖などの習慣
頬杖をつく、片方の顎で噛むなど、片方の顎に負荷をかけすぎると、顎関節に音がするようになります。
➂外傷
転んで顎を強くぶつけてしまうなど、何らかの衝撃や打撃などか下顎骨に加わることで瞬間的に強い力が顎関節に加わり、関節円板のずれを引き起こすことがあります。
音が鳴る原因が顎関節症の場合、早期に対処することが重要です。痛みが出るなど、症状の悪化に繋がる可能性があります。
また、音が『コリッ』『ポキッ』などの破裂音から『ジャリジャリ』や『ギシギシ』などの捻髪音に変化してきた場合は顎関節症が悪化してきているサインの場合もあります。
2. 顎関節から音はするけど痛みがない場合も顎関節症?
顎関節症では、必ずしも痛みを伴うわけではありません。音がするだけで痛みがないケースもあり、この場合でも顎関節症の一種とされています。特に、初期段階では痛みを感じないことが多く、音だけが気になる状態が続くこともあります。
痛みがなくても以下のリスクがあるため、注意が必要です。
①顎関節症の症状の進行
顎関節症の初期段階では音だけで痛みを感じないことも多いですが、放置すると症状が進行し、後に痛みや開口障害が生じることがあります。
➁顎の周囲のの筋肉の疲労
音がする際には、顎の筋肉が不自然な動きをしている場合が多く、筋肉に負担がかかっています。この負担が蓄積されると、痛みやこわばりが発生するリスクが高まります。
➂噛み合わせや歯への影響
音が鳴る状態が続くと、顎関節や歯に負担がかかり、歯や噛み合わせの不調が生じることもあります。
④骨の形態変化
常に顎関節部への圧迫が続くことで骨が病的に吸収し形が変わってしまうことがあります。
これによって顎変形してしまって顔貌そのものが変化するリスクもあります。
音だけで痛みがない場合も、顎関節に異常がある可能性があるため、できるだけ早く歯科医師に相談し、対処法を検討することが推奨されます。
3. 顎関節症で顎を動かすと音がする際の対処法
顎関節症で顎を動かす際に音がする場合、まずは歯科医院の受診が大切です。顎の音や違和感の原因を正確に把握するためには、歯科医師による診断が必要です。
歯科医院では、レントゲンあるいはM R Iで顎関節の状態を詳しく確認します。
歯科医院での診断や治療と並行して、自宅でできる自己対処法もあります。日常的に顎に負担をかけないように気をつけることで、症状の悪化を予防しやすくなります。自宅でできる自己対処法を以下に紹介します。
①食事は両側で噛む
顎にかかる負担をバランスよくすることが重要です。食事は両方のあごを使い、右で5回噛んだら左で5回噛む、というように揃えます。
➁ストレスのケア
顎関節症の悪化にはストレスも関係しています。リラックスできる時間を意識的に作り、ストレッチや深呼吸、軽い運動などを取り入れると、顎周辺の筋肉の緊張がほぐれ、症状が和らぐことがあります。
➂顎周囲のマッサージ
顎周りの筋肉がこわばっているときは、マッサージも有効です。温かいタオルや、暖かいお風呂に入って顎周辺の筋肉をリラックスさせましょう。
④あくびをする
顎関節症の治療は、まず開口訓練です。顎を動かしますが、あくびのような動きが一番理想です。
⑤顎関節症の原因となる習癖をやめる
頬杖をついたり、スマホなどで目線を落とす時間が長いと、顎の関節の負荷がかかります。
4. 顎の違和感や口が開かないのも顎関節症のせい?
顎関節症には、音がするだけでなく、違和感、こわばり、痛み、口が開かないといった症状が出ることもあります。これらの症状が見られる場合、顎関節症が進行している可能性や、他の疾患の可能性もあるため、早めの対応が重要です。
①顎の違和感やこわばりの原因
顎関節症では、顎を動かす筋肉が緊張することが多く、これにより違和感やこわばりが生じます。口を開閉するたびに顎に不快感が生じるようになると、顎関節症が悪化している可能性があります。
➁口が開かない(開口障害)の原因
顎関節症が進行すると、口を開ける際に関節がうまく動かず、十分に開けられなくなることがあります。これは、関節円板のずれや筋肉のこわばりが原因で起こる「開口障害」と呼ばれる症状です。開口障害が進行すると、日常生活に支障をきたすため、早期の治療が望まれます。また、破傷風という細菌に感染すると、急激に開口障害が現れることがあり、速やかな対応が必要です。
まとめ
顎を動かしたときに音がする場合、顎関節症が原因である可能性があり、放置することで顎関節症状が悪化するリスクがあります。音がするだけで痛みがない場合でも、早期に対処することで、顎や筋肉への負担を軽減し、さらなる進行を防ぐことができます。
違和感や口が開かない症状が見られる場合は、顎関節症の他にも感染症の可能性があるため、早めに歯科医師の診断を受けましょう。
関歯科診療所では、顎関節に生じる疾患の診断や治療を行っています。顎の音や違和感に悩まれている方は、ぜひ一度ご相談ください。
監修
関歯科診療所
院長 関 豊成